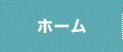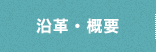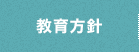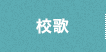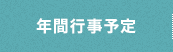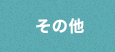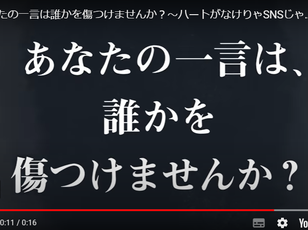生徒人権集会 「誰か」のことじゃない
更新日: 令和6年 12月 12日
![]()
生徒会主催による生徒人権集会が開催されました。始めに、宇﨑さん(2年)の人権作文の朗読を聞き、人権意識を高める手立てとしました。講演会では、人権擁護委員の石毛先生から「いじめについて」の講話を聞き、いじめの構造や対処方法を考えることができました。
生徒の皆さん、今後の人生において、様々な立場から一人一人の人権をいつも意識していくことが大事です。
生徒会が司会を務めます。
『人権週間』についての説明です。
【人権週間について】
1948年12月10日の国際連合第3回総会において世界人権宣言が採択されたことを記念して、1949年に法務省と全国人権擁護委員連合会が世界人権デーである12月10日を最終日とする1週間(12月4日~12月10日)を人権週間と定めました。
いじめや児童虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障害等を理由とする偏見や差別、ハンセン病問題など、様々な人権問題が依然として存在しています。これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、「誰か」の問題ではなく、自分の問題として捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。(法務省ホームページから抜粋)
第76回人権週間 令和6年12月4日(水)~12月10日(火)
- 人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」公開中
 !←クリック
!←クリック
【人権作文の紹介】
神崎中学校では、2・3年生が夏休みの選択課題として人権作文を書き、代表作品を全国中学生人権作文コンテスト香取協議会大会に出品しています。
宇﨑さん(2年)の作品紹介です。
『大きな壁』 宇﨑 真之助(2年)
僕はMK-Ⅴ(マーク・ファイブ)を初めて見たとき、「腕を切ろうかな」と思いました。僕が初めてMK-Ⅴを知ったのは、まだ幼いときでした。MK-Ⅴはモーターが組み込まれた、レゴブロックで作られた義手のことです。
デイヴィット・アギュイラーさんが初めてレゴブロックで義手を作ったのは、わずか九歳のころでした。18歳のときには完全に義手として機能するモデルができ、赤いボディからアイアンマンのインスピレーションを受けて、MK-I(マーク・ワン)と名付けました。
デイヴィットさんは、ポーランド症候群という、胸筋や腕、肩や手の筋肉の発育に異常を起こす先天性の病気のため、右腕が発育不全で生まれました。そのことから、幼少時代に心無い言葉を投げかけられたことも多かったそうです。デイヴィットさんは、その想像力を使い、自分の世界へ没頭しました。そうすることで、外の心無い言葉から自分の身を守っていたのです。ゲームやコミックに夢中になり、特にレゴブロックでは、今にも飛び立ちそうな飛行機を作れるほどになりました。デイヴィットさんは、「レゴは僕にとって初めてのおもちゃだった。これさえあれば、何でも自分で作れるんだという気持ちになったのを覚えている」と言っています。そんなデイヴィットさんを支えているのは彼の父親です。デイヴィットさんの父親は彼を特別扱いすることなく、当たり前のように一緒に遊んでいました。デイヴィットさんは、その想像力や父の支えもあり、『世界初のレゴ製の実用可能な義手』『世界初の足で操作するレゴ義手』『世界初のタッチペン付きのレゴ義手』という三つのギネス世界記録を所持しています。
2016年7月、神奈川県の知的障害者施設で、19人が死亡、37人が重軽傷を負う殺傷事件がありました。その事件の犯人である元施設職員の男は、何年経っても「重度障害者は安楽死させるべき」という思想を持っており、自分は殺人鬼ではなく、社会を重度障害者から解放した『救世主』であると主張しています。僕はこの記事を読んでから、心がモヤモヤしています。本当は「今すぐ死にたい」と思っている人がいるのか、僕が障害者になったらモヤモヤが収まるのかとさえ考えました。
しかし、僕はあることを思い出し、心の中のモヤモヤがほとんどなくなりました。それがデイヴィットさんと、その父親です。僕は、デイヴィットさんの父親のようになりたいです。特別扱いすることなく、当たり前のように接する人に。この考えは、一つ上の先輩が書いた、障害者目線の人権作文を読んで、更に深まっていきました。
「障害」とは、左手が無いなどの身体障害、ADHDなどの発達障害、うつ病などの精神障害、知的障害などのことを言います。そんな障害を持っている人、「障害者」はかわいそうなのでしょうか。僕は今まで、障害者には優しくするべきと思っていました。ですが、デイヴィットさんは障害のことを「異なる能力」と表現しています。先輩は「病気や障害を気にせず接してくれる友達が、大きな支えになっている」と言っています。僕は驚きました。僕は障害をデメリットだと思っていましたが、障害者は生活の不自由で障害を言い訳にしません。障害者を、かわいそうだと思うのは違います。障害者は何度も壁にぶつかっている人ではなく、理不尽な壁を何度も乗り越えてきた勇敢な行動家たちです。デイヴィットさんは、障害のことを「異なる能力」と表現しており、障害を良い方に考えています。それで三つのギネス記録をとったデイヴィットさん。僕も彼を見習い、何かできなくても決してあきらめない人になりたいです。
神奈川県の事件とデイヴィットさんのこと、先輩のことを、一くくりにしてしまうのは無理があるかもしれません。ですが、僕がデイヴィットさんの作ったMK-Ⅴの格好良さに腕を切りたいと思ったほどに憧れ、先輩の作文を読んで先輩の力強さを知ったのは事実です。
【講演】『いじめと戦おう』 講師 人権擁護委員 石毛先生
生徒人権集会 講演の部です。
【講師】人権擁護委員の石毛先生
いじめに関するビデオ視聴
内容についての質問に答えます。
いじめの場面について答えます。
「あり得ない行動だと思います。」
周りの言動が変わることが大事です。
生徒会長から生徒代表お礼の言葉
【 講演の感想 】
- 私は今日の講演を拝聴して学んだことがたくさんありました。たとえば、いじめられている人がいたら見て見ぬふりをせず、相談に乗ってあげたり、助けたりすることが大切だと思いました。さらに、自分がされたらどう思うかを考えて行動したいと思いました。これまでの私だったらどうしていいか分からず、見て見ぬふりをしてしまうと思います。もし、いじめられている人がいたら、今日の事を思い出して対処したいです。 今井さん(1年)
- いじめは日常的に聞かないので、今回動画を見たりお話を聞いたりしてこんなに怖いものなんだなと思いました。軽い気持ちでその場を流さないで、注意したり大人の人に言ったりしようと思いました。まずはやらないことが一番だし、見て見ぬふりは絶対にしません。止める勇気と、言う勇気をもって行動したいと思います。勇気が出なかったら、友達など言いやすい人に声を掛けたいです。 椿さん(1年)
- 私が心に残ったのは、動画に出てきたお姉さんからの助言です。いじめに遭遇したら、見て見ぬふりをしないとか、一緒になって笑わないという内容でした。また、いじめられている人から変えるということでした。そんな発想はなかったから、すごいと思いました。これから私は、それにプラスしていじめられている人の味方になっていきたいです。 奥田さん(2年)
- いじめについてのDVDを観て、いじめている人は3人位だったけど、それを見て笑っているだけの人もいじめている人に入るのだと思った。いじめられている人は決して悪くないけど、いじめる人のターゲット探しで下に見られないように印象を良くすることも大事なことだと思った。いじめが起こらないように周りの人の個性や性格を大事にしたいと思った。 大野さん(2年)
- 私が講演を拝聴して考えたことは、いじめは絶対してはならないということです。いじめをしても、誰も嬉しくありません。いじめられている人は、いじめてくる人や見て見ぬふりをする人が全員敵に見えて自殺にまで追いこまれてしまうこともあります。もし、いじめの現場を見たら、相手に優しく声を掛け、相談相手になれるようにしていきたいです。周囲の環境によって変わることもあると思うから、やっていいこと、ダメなことをちゃんと理解してこれからの生活に生かしていきたいです。 髙柳さん(3年)
- 講演を拝聴して、周りの人の役割がとても大切だということが分かりました。また、いじめられている人も、やめてほしいときちんと言えることも大切だと思いました。もし自分がいじめを目撃してしまったら、しっかり注意などをすることや、いじめられている人の味方となり相談にのってあげることも大切だと思い、これからの教訓としていこうと思いました。 三澤さん(3年)